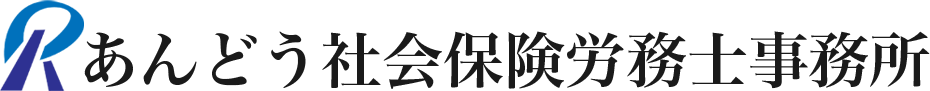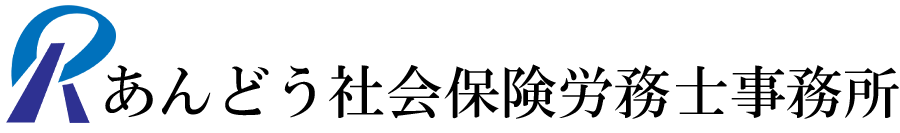4月の改正ポイント「労働条件明示ルール」

今回は4月の改正ポイントとして「労働条件明示ルール」。それにまつわる労働契約に関する法律を2つご紹介します。
まずは、労働条件明示のルール変更です。
1.令和6年(2024年)4月の改正点
労働者の募集時等や、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。
(1)全ての労働者に対する明示事項
就業の場所・業務の内容については、「雇い入れ直後」に加え、これらの「変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)」を明示します。
(2)有期契約労働者に対する明示事項
- 更新上限の明示(更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示)
- 無期転換申込機会の明示(無期転換権が発生する更新のタイミングごとに明示)
- 無期転換後の労働条件の明示(同上)
※有期労働契約の通算契約期間や更新回数の上限の明示(改正労基則5条1号の2)のほか、更新上限を新設・短縮する場合の説明が必要になります。通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間を指します(労働契約法18条1項)。
厚生労働省は、「更新回数は3回まで」「通算4年を上限」などとする例を示しています。
Q&Aでは残りの契約更新回数を書く方法も、労使双方の認識が一致するような明示なら差し支えないとしています。ただし、なお書きで、当初から数えた更新回数または通算契約期間の上限を明示し、そのうえで、現在が何回目かの更新であるかを併せて示すことが考えられるとしています。単に回数だけの明示だと、もともと1年契約だったのが更新で半年になった場合など労使で認識に相違が生じることがあるため、上限期間も明示しておくべきとあります。
次に労働条件の明示とは?労基法15条をおさらいしましょう。
2.労働条件の明示事項(労基法15条1項、労基則5条)
(1)書面で明示すべき労働条件
- 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(満了後に更新する場合があるもの)
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など)
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)その他明示すべき労働条件
- 昇給に関する事項
- 定めた場合に明示すべき事項(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項)
※職安法5条の3、職安則4条の2:「試用期間」、「加入保険の適用」、「募集者の氏名または名称」、「派遣労働者として雇用する場合はその旨」、「受動喫煙防止措置の状況」を募集や求人申込の際に、書面で明示する必要があります。
※パート・有期雇用労働法6条、則2条:「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより、パート・有期雇用労働者に明示する必要があります。
(3)明示の内容
上記(1)②は、有期契約労働者が「契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要」します(平24・10・26 基発1026第2号)。
同④は、「勤務の種類ごとの始業および終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足り」ます(平11・1・29 基発45号)。
同⑤は、「賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えない」としています(昭51・9・28 基発690号)。
今日はもう一つ。個別労働関係紛争を防止するために、労働契約の内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないよう、労働契約法もご紹介しておきます。
3.労契法4条1項
「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と規定しています。
労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者および使用者の合意のみにより成立する契約です。しかし、契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を締結または変更すると、後にその契約内容について労働者と使用者との間において認識の不一致が生じ、これが原因となって個別労働関係紛争が生じることがあります。こうした紛争防止のために、使用者は労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにすることを規定したものです。
1.条文の解説
(1)労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結または変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものです。これは、労基法15条1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものです。
(2)「労働者に提示する労働条件」とは、労働契約の締結前または変更前において、使用者が労働契約を締結または変更しようとする者に提示する労働条件をいうものです。
(3)「労働契約の内容」は、有効に締結または変更された労働契約の内容をいうものです。
(4)「労働者の理解を深めるようにする」については、一律に定まるものではありませんが、例えば、労働契約締結時または労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、使用者がそれを説明しまたは労働者の求めに応じて誠実に回答すること、労働条件等の変更が行われずとも、労働者が就業規則に記載されている労働条件について説明を求めた場合に使用者がその内容を説明すること等が考えられるものです。
2.書面確認(2項)
2項では、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」と規定しています。
「できる限り書面により確認する」とは、一律に定まるものではありませんが、例えば、労働契約締結時または労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、労働者および使用者が話し合った上で、使用者が労働契約の内容を記載した書面を交付すること等が考えられるものです。
「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」には、有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準(平15・10・22厚労省告示357号、令5・3・30厚労省告示114号)において使用者が明示しなければならないこととされている更新の有無や更新の判断基準が含まれるものです(令5・10・12基発1012第2号)。
いかかがでしょうか。なかなか細かなルールもあり、一読で理解は難しいと思います。それでも、この部分の抜け落ちは後々、大きな落とし穴になりえて、労使間のトラブルを避けるためには必須事項と言えます。ぜひご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。