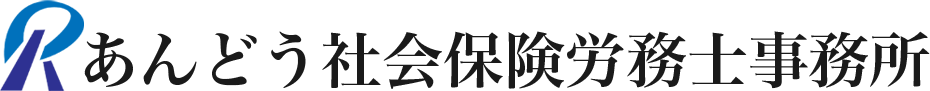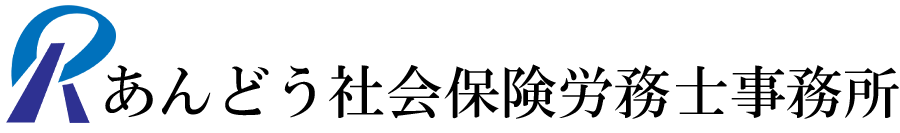賃金のデジタル払い

みなさん、こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。
今回は、最近の労働法改正に関連する「賃金のデジタル払い」に関する最新情報をお届けするとともに、中小企業の事業主が今後留意すべきポイントについてもお伝えします。
賃金の支払方法の新たな選択肢
賃金の支払方法については、従来から「通貨の支払い」や「労働者の同意を得た銀行等の金融機関の口座への振込み」が認められてきましたが、令和5年4月1日より、これに加えて「厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動」も新たな賃金支払方法として認められるようになりました。これにより、いわゆる「賃金のデジタル払い」が可能となり、企業にとっては給与支払いの選択肢が広がることになります。
PayPay株式会社が初の指定を受ける
この改正の施行後、しばらくは指定を受けた資金移動業者が存在しませんでしたが、令和6年8月9日、ついに「PayPay株式会社」に対して、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定が行われました。これにより、PayPayの口座を利用した賃金支払いが法的に認められ、デジタル技術を活用した新たな給与受取の選択肢が提供されることになります。
なお、サービスの開始時期については、PayPay株式会社からの公式発表を確認していただく必要があります。具体的なサービス提供時期については、こちらのリンクから詳細をご覧ください。
中小企業の事業主が今後留意すべきポイント
中小企業の事業主にとって、賃金のデジタル払いを導入する際には、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。
- 労使協定の締結と労働者の同意の取得
賃金のデジタル払いを導入するためには、各事業場での労使協定の締結および労働者本人の同意が必要です。法令上は「労働者の同意」を得ることが義務付けられていますが、厚生労働省の通達により、労使協定の締結も求められています。これにより、企業が一方的にデジタル払いを導入することはできないため、事前に十分な説明と協議が必要です。
2. システム導入コストと運用負担
デジタル払いを導入する場合、初期投資として以下のようなシステム導入コストや運用に伴う業務負担が発生する可能性があります。
- 給与計算システムの対応: 既存の給与計算システムがデジタル払いに対応していない場合、新たに対応システムの導入や、既存システムのアップデートが必要となります。このためのソフトウェアの購入費用やカスタマイズ費用が発生する可能性があります。
- セキュリティ対策の強化: デジタル払いでは、給与データや個人情報がインターネットを介してやり取りされるため、サイバーセキュリティ対策の強化が求められます。これには、データ暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査の実施などが含まれ、そのためのシステム導入や保守費用が発生します。
- 従業員のトレーニング: デジタル払いシステムの導入後、従業員に対して新しいシステムの利用方法に関するトレーニングが必要となります。これには、トレーニング資料の作成、研修の実施、さらにはサポート体制の整備が含まれます。これらの取り組みによる業務負担が増加する可能性があります。
3. 労働者からのデジタル払い要求への対応
労働者から賃金のデジタル払いを求められた場合、事業主はそれを断ることが可能です。賃金のデジタル払いは、法的に認められた支払方法の一つであるものの、導入はあくまで任意であり、企業がその準備や体制が整っていないと判断した場合には、デジタル払いに対応しないことも可能です。事業主がデジタル払いの導入に慎重である理由として、システム導入にかかるコストやセキュリティ対策、従業員への説明と同意取得に関する負担が挙げられます。
このため、労働者からの要求を断る際には、なぜ現時点で対応できないのかを丁寧に説明し、双方が納得できるような対応を心掛けることが重要です。
参考リンク:
また、「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」や「令和6年8月掲載のリーフレット」も併せてご参照ください。最新情報を確認し、適切な対応をお願いいたします。
引き続き、皆様にとって役立つ情報をお届けしてまいります。ご不明な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。