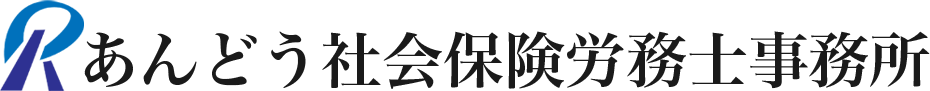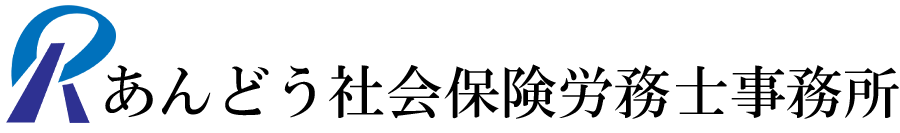先日実際にあった相談事例からご紹介

みなさん、こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。
今回は、先日実際にあった相談事例からご紹介します。
Q『どうも雇用保険に入っていないみたいなんですが、どうしましょう?』
詳しく聞いてみると・・・。雇用保険の被保険者資格取得の手続きがされていないということのようです。手続漏れです、失念や勘違い等もあるでしょう。最初は週当たりの労働時間も短かったのが、気づけば20時間を超えてしまっていた。よくあると言えばよくある事例です。健康保険は保険証が手元に行くことから、労働者、事業主双方気に留めるので手続きが漏れることはあまりないですが、雇用保険は被保険者証はあるものの会社保管等により、労働者の手元に行かないことが慣例となり、双方失念しうる事となります。
とは言え、数ヶ月であれば遡及取得手続で事なきを得ます。
Q『4人・・・かなり前から未加入ですが・・・?』
・・・。非常にまずいです。年度をまたぐのはまずい。労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます)を単位とし、その間のすべての労働者に支払った賃金の総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
みなさまのところには、例年そろそろ労働保険料の手続きの更新書類の入った封筒が届きます。そう、「年度更新」です。確定した前年度の労働保険料(確定保険料)と、今年度の概算保険料を併せて申告および納付する手続きのことです。原則として、6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局および金融機関等で手続きを行います。年度をまたいで未加入の者がいるということは、この例年のチェックに漏れてしまっていることを指します。
労働保険料算定基礎調査
こうなると、労働保険料算定基礎調査、「算調」を受けることになります。簡単に言えば過去の労働保険料の再計算です。
・そもそも労働保険料とは何か?
労働保険料は、事業主が負担する保険料で、以下の二つに分けられます:
労災保険料:労働者が業務上の事故や通勤途中の事故で負傷した場合の治療費や休業補償などに充てられます。
雇用保険料:失業した労働者の生活を支援する失業給付や再就職支援などに充てられます。
・調査の対象と方法
調査の対象は、基本的に直近の2年度分の申告内容です。「確定保険料申告書」の事業主控の提出と過去2年分の賃金台帳を基に「賃金支払関係調査書」の作成提出です。その他、全従業員の労働者名簿や出勤簿などの資料と共に未加入者の「被保険者資格取得届」と「遅延理由書」を添付し提出します。
・調査結果とその対応
調査の結果、不足分の保険料と追徴金(不足保険料の10%)が徴収されます。
・事業主の責任と重要性
事業主は、労働保険料を正確に申告・納付する責任があります。また、遡及加入出来るのは2年です。それを超える期間は遡及できないので、被保険者期間等本人の不利益として発生します。当然、責任を問われる形になります。
このメルマガを通じて、労働保険料算定基礎調査の重要性と手続きを理解していただければ幸いですが、そもそも、この「算調」を受けないために、年に1度は自社の被保険者の状況を把握することを、お勧めします。そのひとつに「雇用保険被保険者数お知らせはがき」があります。
「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とは、雇用保険関連諸手続きの漏れがないかどうかの確認を目的として、各事業所の雇用保険被保険者数や管轄ハローワーク、個人番号登録者数等を通知するものです。 2024年3月に送付されたはがきには、2023年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。このはがきに判を押して管轄ハローワークへ持ってて行けば、簡単に「事業所別被保険者台帳」を入手できます。
自社の現状、雇用保険の資格取得者に漏れがないか、または既に退職した従業員の資格喪失手続漏れがないか、ご確認ください。
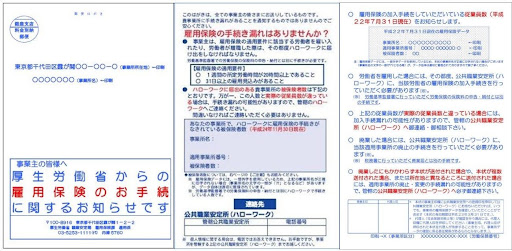
最後までお読みいただきありがとうございました。